2. 臨床検査の精度管理方法は今も昔もずっと間違っている
検査業界で最も多く使用されていて、最もメジャーな精度管理図方法といえば、やはり「Xbar-R管理図(Xbar-Rs-R管理図でも可)」でしょう。
「Xbar」はその日に測定した管理試料の平均値をプロットし、これは「正確さ」を表わしています。
「R]はその日に測定した管理試料の最大値と最小値の差をプロットしており、「その日の精密さ」を表わしています。
「Rs」はその日の平均値と前日の平均値との差をプロットしており、「日間の精密さ」を表わしいます。
臨床検査の現場ではこのXbar-R管理図が最も用いられているのですが、じつはこれ、臨床検査のための管理方法として開発されたものではないのです。
もともと製品工場などで使用されていたものを、臨床検査の場でも使用しているだけであり、臨床検査のためだけの管理方法ではありません。
この事実、知らない人が結構多いです。
検査技師の学校で使用されている教科書にもXbar-R管理図が当たり前のように書かれており、現場でも当たり前のように使用しているので、たいていの人は何の違和感なく使用していますが、まったく別の業界の管理方法を流用しています。
しかし、ぜんっぜん臨床検査の管理方法としては適していません。
なぜなら、一番大切なXbarの部分が「その日の平均値」なので、例えば1回目の測定値が高値で2回目の測定値が管理限界を超える低値であっても、平均化されてちょうど管理幅に余裕でおさまってしまい外れていることに気付けません。
このような場合はその日の最大値と最小値の差を表わす「R」を見れば気付けることもありますが、仮に1回目が低値で2回目が管理限界をやや超えるぐらいの低値ならば管理幅内におさまってしまうのでまったく万能ではありません。
ですので管理上限を超えるような問題が起きていても気付きにくいのがこのXbar-R管理図なのです。
一目で状態が把握できないのは不親切ですし、1つの管理図で日内変動を正確に追えないのも不便です。
臨床検査が始まって以来ずっとこの方法で臨床検査は管理されてきましたので、僕は臨床検査の精度管理方法は今も昔もずっと間違っていると思います。
こんな管理方法で品質管理なんて、本当にできるのでしょうか。
僕はそうは思いません。
ではどうすればしっかりと品質管理していると胸を張って公言できるような精度管理ができるのでしょうか。
シンプルに測定値をそのままプロットして変化を追っていけば良いのではないでしょうか。
あまり意味のない「R」も「Rs」も取っ払い、シンプルに測定値「X」をプロットして今の状態をリアルタイムに反映して管理していくのがX管理図です。
毎日いつどのタイミングで測定した測定値がどう動いているのかがわかりやすく、試薬や機械の状態が一目瞭然でわかる臨床検査に最適な管理方法といえるでしょう。
僕が開発したのでもちろん当院で導入しており、毎日このX管理図で品質管理を行っています。
実際の管理図が下記のようになります。
上記の入力シートにデータを入力すると、下記のようにグラフに描画されます。※下記は3台分入力した例です。
この管理図が欲しい、もっと詳しく聞きたい、運用について相談したいなどがありましたら、このサイト下部からお問い合わせいただくか、TwitterからDMいただければ対応しますので何かありましたらお気軽にどうぞ。
まだ企画段階ですが、今後お問い合わせのあった施設に合わせてX管理図を作成する有料サービスをはじめるかもです。
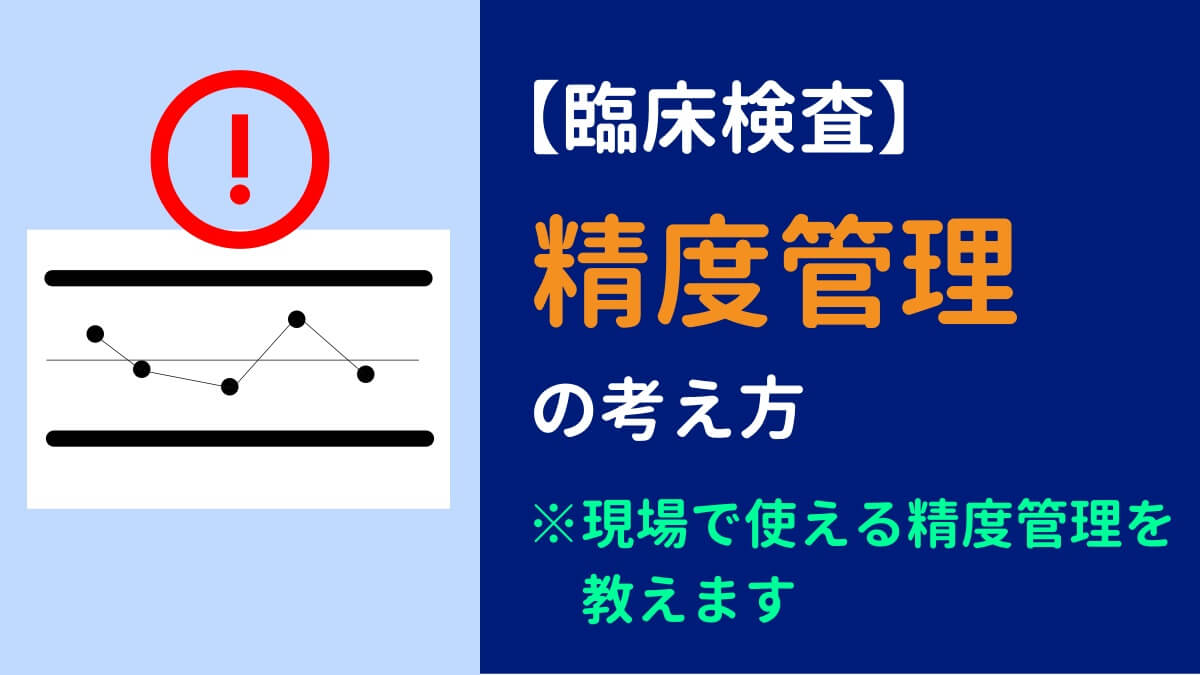




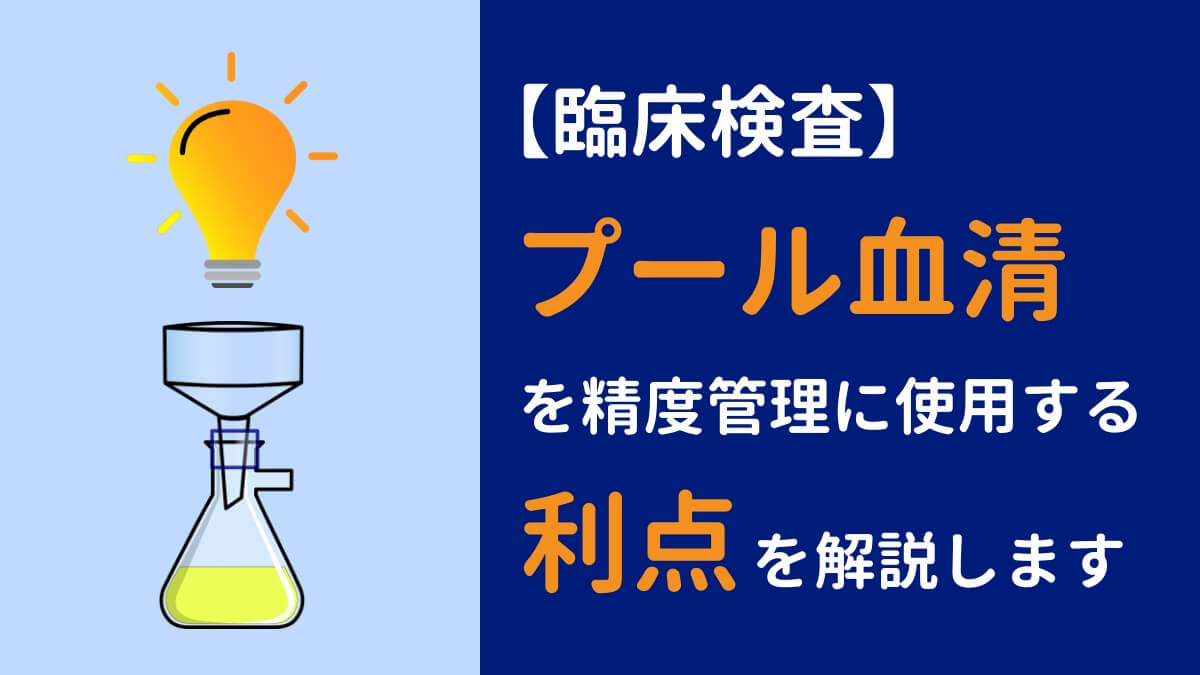
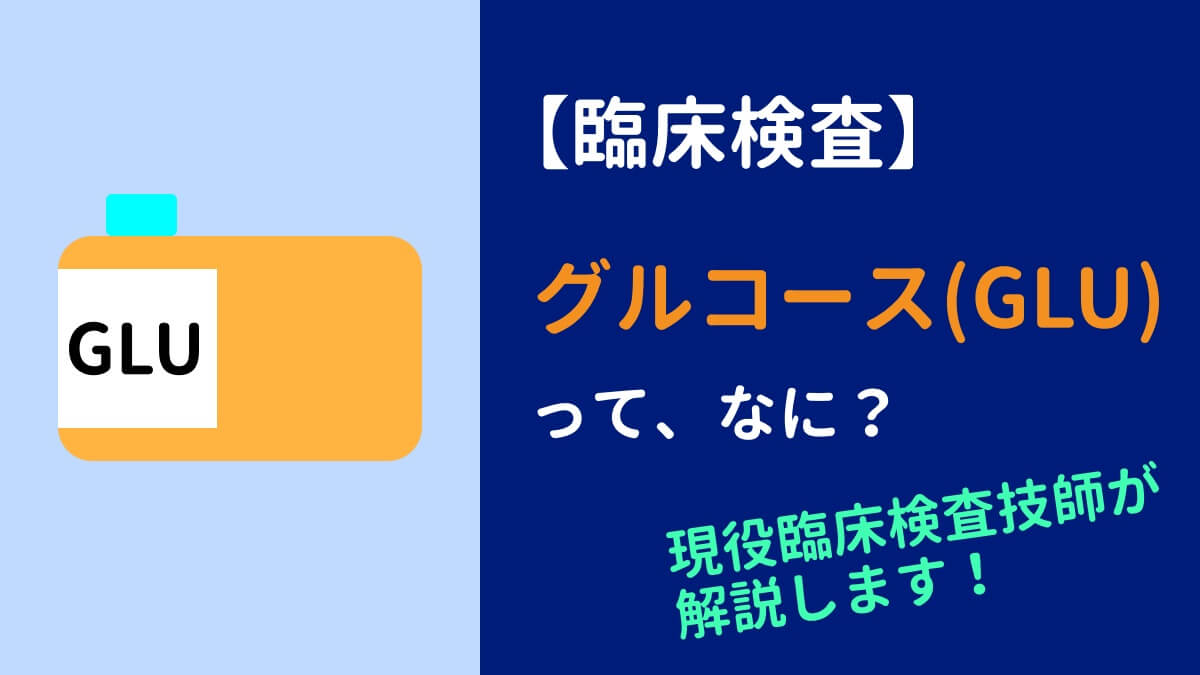
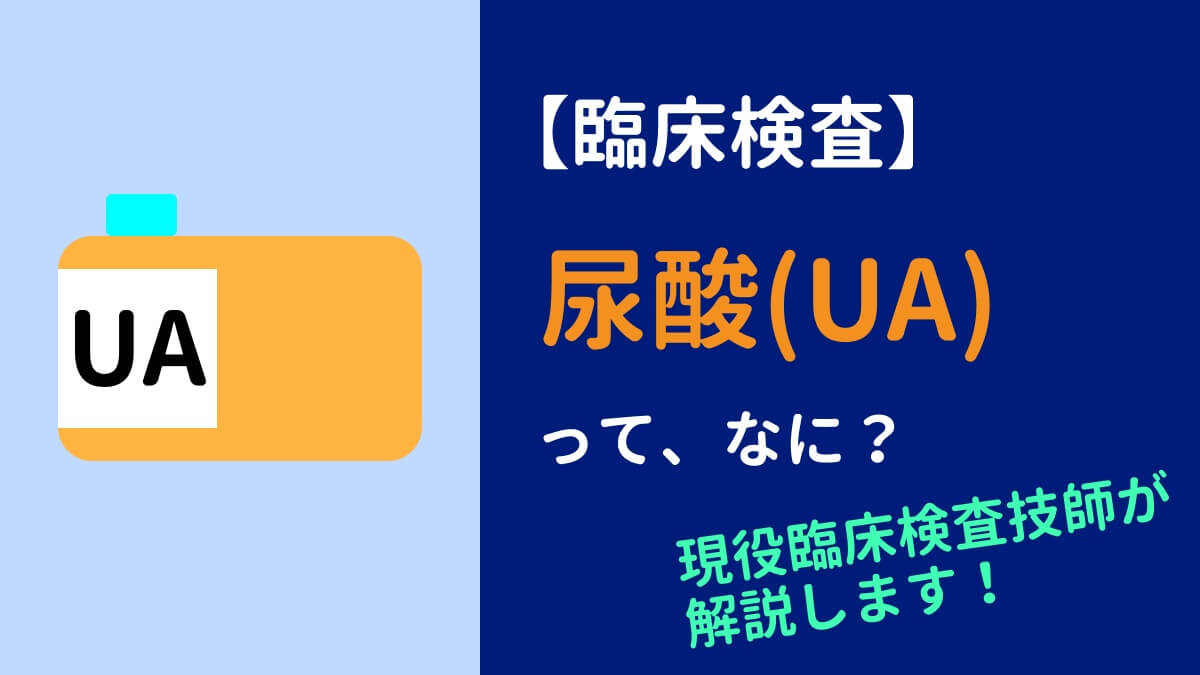
その商品が「しっかりと信頼が担保された安心のできる物ですよ」と裏付けをするのが精度管理です。
ウエノ